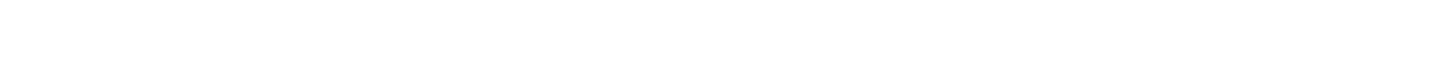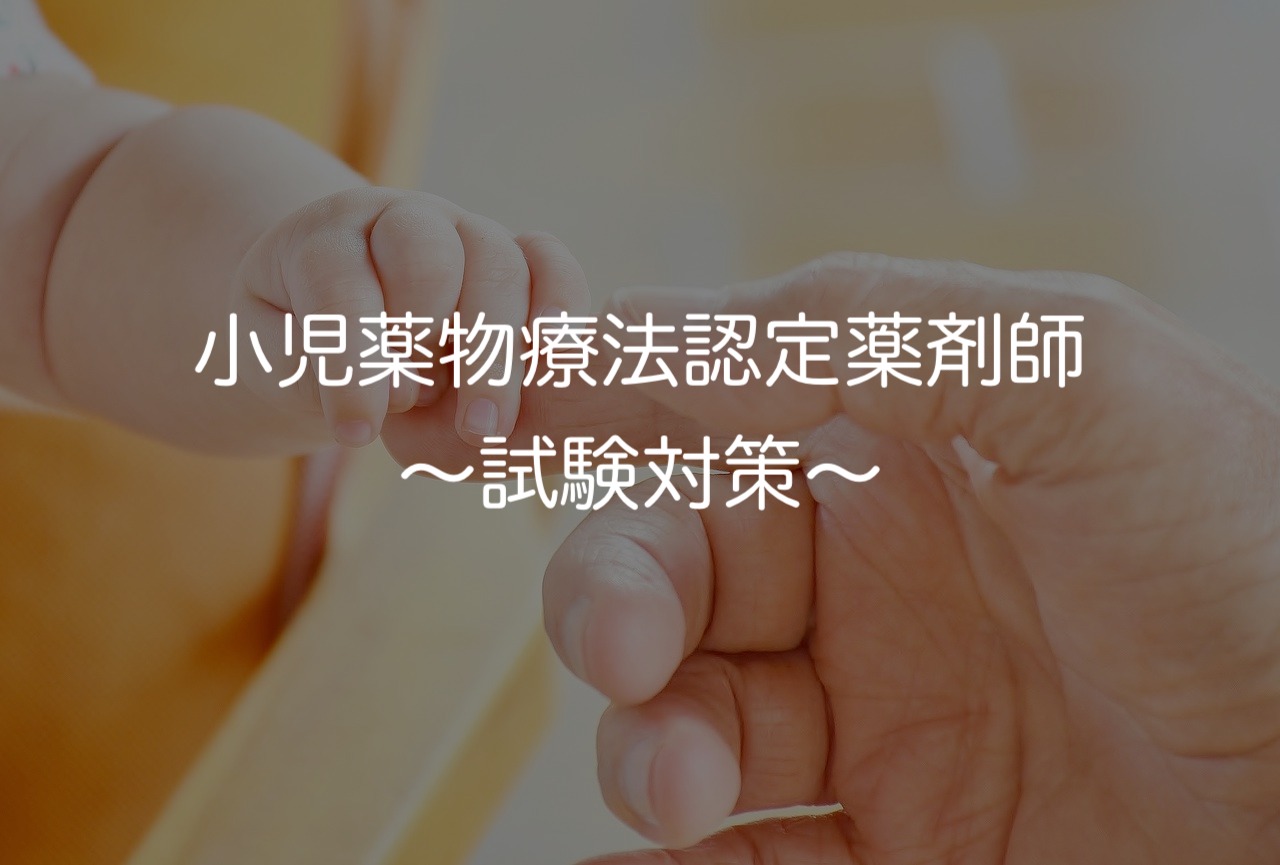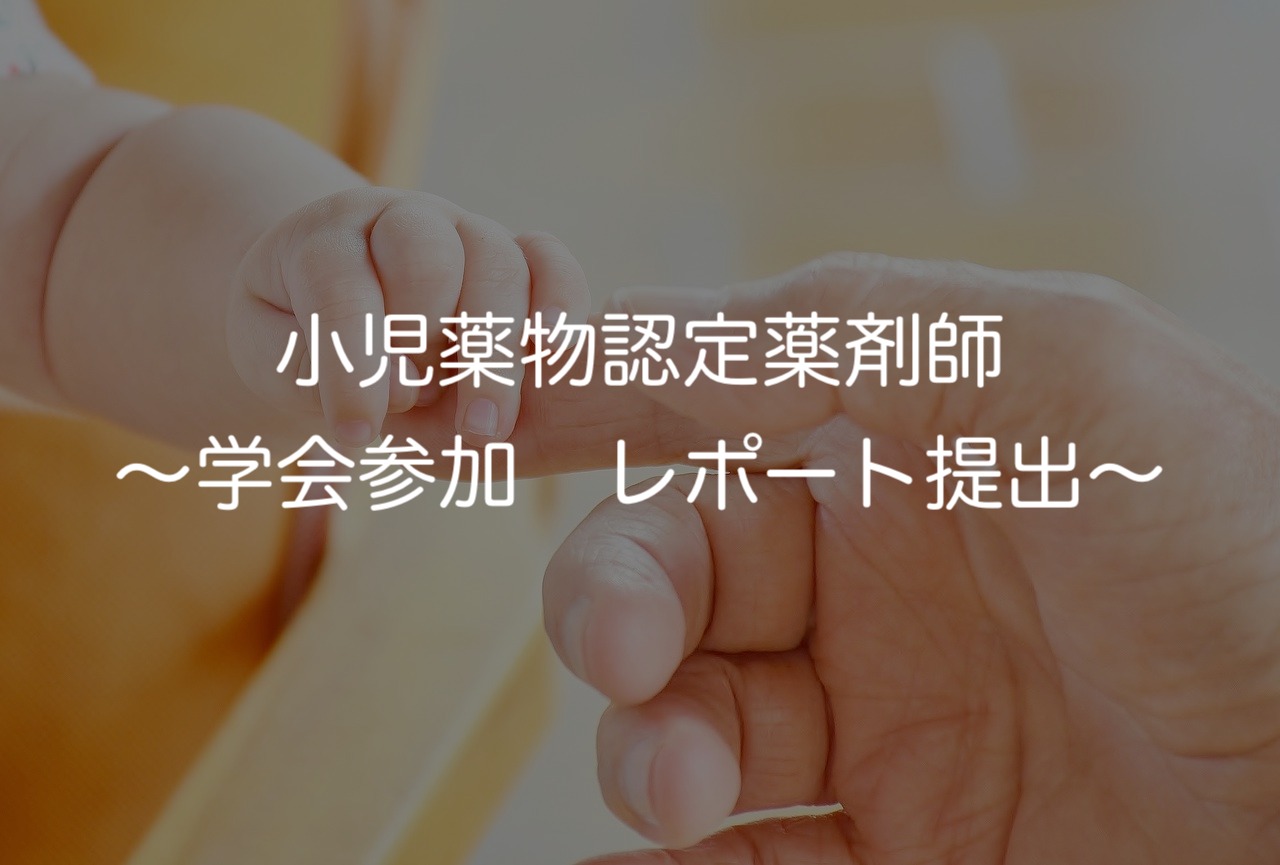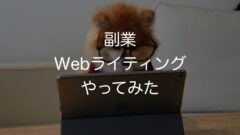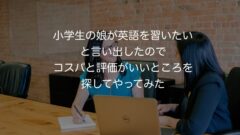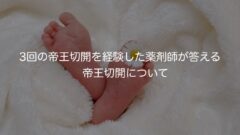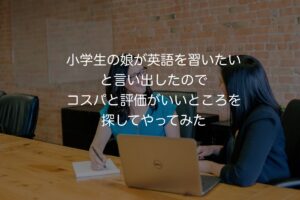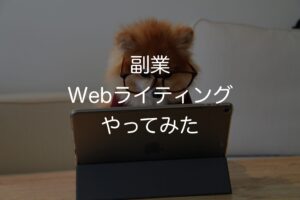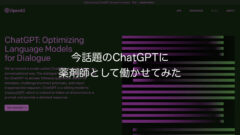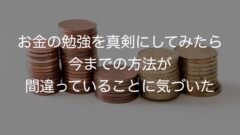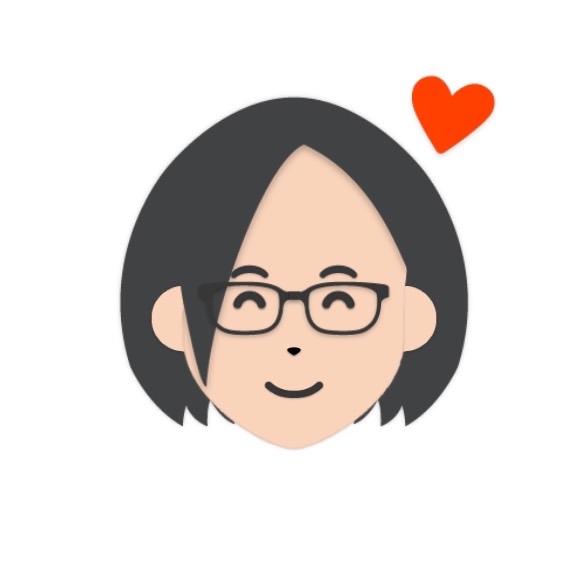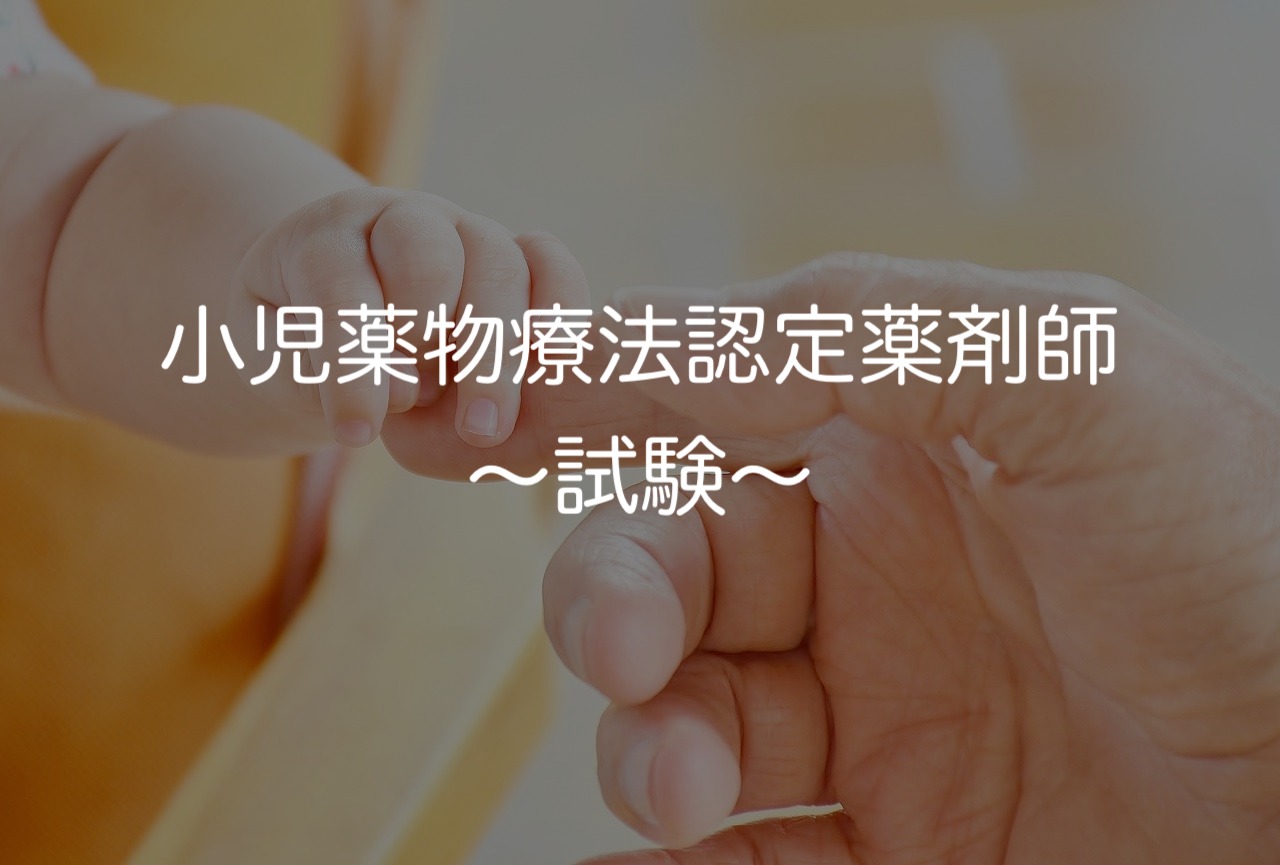
はじめに
無事、小児薬物療法認定薬剤師に合格することができました。
実際うけてみて問題はこんな感じで多分こんな答えかなと分析しました。
注意事項
※個人的な分析なのでそうなんだ程度でご覧ください。
※3問くらい◯✗どっちとも取れるような問題があったので△としています。
※問題は完璧に覚えているわけではないため若干の言い回しなど異なる場合があります。
感想
→あまり発信する人がいないこともありますが、自分が聞いていた話より難しく感じた。(国家試験なみ)今までは倫理観でわかる問題が数多いと聞いていたが、今回は明らかに病態を聞いている問題が多かった。
→1つ選べや2つ選べ、違うものを1つ選べなどがランダムになっている。そもそも読むのに時間がかかるため解くのも時間ギリギリ。
→ぬるっと覚えている程度では解けないものが多いです。全く聞いたことない単語はでなかったが、講義でここまで書いていた、または言っていたかな?という問題が1割ほどあった。講義で重要といっていたことがあまりでていない感じがした。そこ聞くのかよ的なやつ。まあ、大学の試験ではこれはあるあるですが。。。
問題
1歳未満は小児?→✗ 添付文章の場合だと7歳以上15歳未満
小児の年齢別死因5−9歳は悪性新生物の死因が第1位をしめる→✗不慮の事故
新生児は胃酸のPHが低いので酸性薬物の吸収は低下する→✗PHが高い6〜8
グレイ症候群は何が低いため発症するか?→グルクロン酸抱合が低いため
小児で検査値が基準より低いものはどれか→TP(総蛋白)、クレアチニン、アルブミン
検査の基準値とは健康な基準個体から得られた計測値
中毒性肝障害は用量依存性に基づく、アセトアミノフェンによる過剰投与が原因
特異体質性肝障害は通常の薬物投与でも肝障害をきたす。ペニシリンやフェニトインで起こる。poor metabolizer(代謝能が欠損、または低い)、チトクロームP450、Nアセチルトランスフェラーゼが原因。
・MIC値を考慮する→✗判断の材料にしない
・できるだけ広い抗菌スペクトルのものを使用→✗
・耐性菌の可能性が低くなる→✗
・とびひは第一セフェムが第一選択薬である
・ピボキシル基を有する抗菌薬は低カルニチン血症のリスクになる
30年前と比べ低出生体重児は増えている
離乳食は生後6ヶ月が適切である→△人によりけり5から6ヶ月が推奨 講義ごとのスライドで言っていることが異なるため微妙
離乳食を開始したら母乳は徐々に減らす→✗変えない
離乳食にレバーや赤い魚、牛は用いない→✗問題なし
小児は成人に比べ細胞内液の割合が多いため脱水になりやすい→✗細胞外液の割合が成人に比べ多い
中心カテーテルは上大動脈内に留置→✗大静脈内
NPC/N比は成人に比べ小児の方が高い
生後3ヶ月までは母乳やミルク以外のタンパク質の分解が困難なので生まれてすぐに離乳食を始めない。
小児に通常の経腸用栄養剤を投与するとビタミンD、カルニチンが不足する可能性がある
経腸用栄養剤を投与する小児はてんかんが最も多い→✗ 具体的にどこも書いてない
経管栄養法で小児ではメチオニン、フェニルアラニンを減量している
肺サーファクタントの欠乏で起こる病態はどれか→呼吸窮迫症候群(RDS)
出生時のシトクロムP450の活性は極めて低い
胎児期、新生児期ともに成人とくらべ腎血流量は少ない。1歳頃に成人と同等になる。
ダイアップ座薬は水溶性、アンヒバ座薬は油脂性でダイアップから先に挿入し30分以上感覚をあける
ゆっくり吸う→✗素早く吸う
カウンターが0になったらレバーはひけない→✗ひける
必ずうがいをする→ステロイド入ってなければ必ずとういうわけではないが、メーカー等推奨しているので◯と解釈、あと◯がこれしか選択肢がなかった気がする
皮下免疫療法と舌下免疫療法は舌下の方がアナフィラキシーが起こりづらい
ミティキュアとシダキュアは同時に始めることがいい→✗メーカーより避けるの推奨
ICS懸濁液は電子式ネブライザーのジェット式、超音波式、メッシュ式すべて用いることができる→✗超音波不可
汎用性の恐れのある医薬品で厚労省が警報を出していないものはどれか→出しているものはエフェドリン、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロムワレリル尿素
ICHE11ガイドライン→小児集団における医薬品の臨床試験に関するガイダンス
小児医薬品開発ネットワーク→製薬企業が連携し、国内で優先的に開発スべき医薬品リストを作成し、小児医薬品の臨床試験を効率的に実施するための体制。
ステロイドを塗ると皮膚が黒くなる→✗血管を収縮するので白くなる。黒くなるのは炎症が酷くなった時
プロアクティブ療法はステロイド中心で保湿は必要ない→✗保湿も重要。
JAK阻害やタクロリムスはステロイドでいうⅣ郡に分類される→✗内服JAK阻害はⅠ、Ⅱ郡相当
ステロイド外用薬は白内障などをひきおこすことがある→△講義スライドでズレあり。原因といっているものもあれば、必ずしもそうと限らないといっているスライドがある。
成人と同様の採血時点で問題ない→△そもそも個人で採血結果をもとにピーク取ることある。または薬剤によりけり。そう考えると◯でも✗でも考えられる。
メトトレキサートはトラフを取ればいい、→✗投与開始24、48,72時間後採血
投与設計はクレアチニンと分布容積で考える。
バンコマイシンはトラフ15μg/ml以上は腎機能リスクとなり推奨されない
小児の腎機能はSchwartzの式がもっとも信用できる。
腎臓からの薬物排泄は胎児週数+出生後日数が34〜35週で急激に上昇する。
川崎病の初期治療は免疫グロブリン+アスピリンが一般的である。
PCR検査について、最近では自動化が進み迅速かつ簡便な製品も登場してきている。
HSV(単純ヘルペスウイルス)→アシクロビル、バラシクロビル
CMV(サイトメガロウイルス)→ガンシクロビル、バルガンシクロビル、ホスカルネット
小児のワクチン定期接種はつぎのうちどれか→B型肝炎と肺炎球菌を選ぶ ✗にA型肝炎、インフルエンザなどあった
溶連菌感染症後急性糸球体腎炎の治療で用いられないものはどれ→用いられるものは安静、塩分水分制限、フロセミド、降圧薬(Ca拮抗薬)、透析療法
家族性のてんかんは良性のものが多い
ADHD治療薬で患者登録が必要な薬剤はどれ→メチルフェニデート(コンサータ)、リスデキサンフェタミン(ビバンセ)
患者に意識がない場合でも胸骨圧迫は行うべき
小児用フェンタニルについて静脈投与に加えて硬膜外やくも膜下にもつかわれる
30年前にくらべ医療的ケア児は増えてきている
ビンクリスチン→末梢神経障害
L-アスパラギナーゼ→アナフィラキシーショック、膵炎
ドキソルビシン→心機能異常
メトトレキサート→腎障害
アイクロフォスファミド→出血性膀胱がん、腎障害